
会員インタビュー 量子ICTフォーラムは産学官の新たなビジネスモデルを創出する場
一般社団法人 量子ICTフォーラム 技術担当理事 荒川泰彦
光バブルが弾けた時
産業界を救ったのは産学官連携の組織だった
いま、量子ICTへの期待が日毎に高まっている。イノベーションを加速し、そのポテンシャルを存分に引き出すためには、周辺技術の進化が欠かせない。その鍵を握る領域が、量子ICTフォーラム技術担当理事、荒川泰彦(東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構特任教授)が文科省Q-LEAP(光・量子飛躍フラッグシッププログラム)でプログラムディレクターを務めている量子計測・センシング技術領域である。
荒川は、マラソンに喩えながら、目まぐるしくトップ集団が入れ替わる量子ICT分野の今後の展開を、研究者ならではの時間軸から描いていた。革新的技術は「オシレート(振り子状反復)しながら上がっていく」。この時間を入れ込む必要がある、と。
(取材:加藤俊 /撮影:古寺正樹)

ここ数年で量子コンピュータの実用化が朧気ながら見えてきたが、世間が期待する能力が実社会で発揮できるまでは、まだ道のりがある。量子コンピュータ開発が踊り場を迎える可能性もある。荒川は「大事なことは息切れをさせないことだ」と訴える。量子コンピュータ開発が停滞しても量子コンピュータ以外の量子ICT全体が進化していけば、量子技術関連産業が興隆する。それは量子ICTへのさらなる投資を呼び込み、指数関数的な市場の広がりにつながる。
そのためには産官学の連携が大きな役割を果たすと荒川は確信している。なぜなら、量子ドットレーザの実現、社会実装に至るなかで身を持って体験しているからだ。
量子ドットレーザの実現可能性が見えてきた2000年頃、ターゲットとしていた光通信市場が一気に縮小し、光バブルは弾けた。産業界の研究者は頭を抱えたが、ちょうどその頃、荒川は文部科学省から大型国家プロジェクトを受託し、産学官連携の「ナノエレクトロニクス連携研究センター」を東京大学で立ち上げ、そのセンター長に就任した。荒川は、この連携研究センターに、東芝、NEC、日立製作所、富士通研究所などの企業研究者を招へいし、本格的な産学連携研究の推進を開始した。2004年には、富士通研究所と共同で、高性能量子ドットレーザの実現に成功することにより、1982年の論文の理論予測を自ら実証した。
荒川は後にこうした幾多の功績も買われ、日本人として3人目の光科学技術の国際連合組織である国際光学委員会(ICO)の会長に2014年に3年間の任期で選出された。イブン・アル・ハイサムの光学研究、フレネルの光の波動説、アインシュタインの一般相対性理論、カオの光ファイバの提唱など、光科学・技術に関わる歴史的に著名な学者や研究者が、偉大な業績を残してから1000年、200年、100年、50年など、節目の年となった2015 年(国連が定める「国際光年」)に、会長として日本でも1200人規模のシンポジウムを東大安田講堂で開催し、物理学の偉人たちに敬意を表している。
未来を覗き見ることは叶わないが、数十年先の未来に、現在の量子ICTのプレーヤー達もまた、文明を進化させた偉人として敬意を表されているだろうことは想像に難くない。

アインシュタインに「神はサイコロを振らない」と言わしめた
若手物理学者たち
およそ100年前、一握りの若手物理学者たちによって新たな物理学の扉が開かれつつあった。ニールス・ボーア、エルヴィン・シュレーディンガー、ポール・ディラック、ヴェルナー・ハイゼンベルクといった稀代の俊英たちだ。彼らはすでに完成されたかに思えた従来の物理学を覆す現象を次々と発見し、それを解明する新たな論理を導き出した。「20世紀は量子力学の世紀だった」と言わしめるほど、そのインパクトは凄まじく、20世紀を代表する物理学の巨星、アインシュタインですら当初、彼らの導き出した論理に対し、「神はサイコロを振らない」と拒否したほどだった。彼は観測される現象が偶然に選ばれる量子力学のあいまいさが納得できなかった。
だがその後も、“ありえない”現象は続々と発見され、解明され、新たな法則が紡ぎ出されていった。彼らの英知は量子力学という新たな物理学を切り拓き、従来の物理学を“古典”に置き換えていった。
やがて一群の若手物理学の俊英の首には、ノーベル賞のメダルがかけられていった。いずれも30代半ばでの受賞という、今日の受賞者の年齢からすれば“ありえない”ほどの若さだった。
先駆者のひしめく半導体レーザに最後発から挑む
これら量子力学の先覚者の躍動を科学史として眺めていた日本の若手電子工学者がいた。東京大学の生産技術研究所に講師として着任した荒川である。荒川は1952年の生まれ。父は名古屋大学物理学教授だった故荒川泰二。物理学の叢書として名高い、『朝倉物理学大系』(朝倉書店)に繋がる『朝倉物理学講座』では『電磁気学』などを担当し、他にも『力学』『力学概論』といった書籍がある父の背中を見て育った荒川は、同じように、アカデミアの世界に入る。量子力学の先覚者たちからは二周りほど若かったが、量子力学が持つ技術展開の可能性に早くから関心を持っていた。

荒川はもともと通信理論の研究で工学博士の学位を取得していた。大学院修了後に半導体レーザに専門を転換した直接的理由は、東京大学の生産技術研究所の若手教員の席が空いたが、光デバイスを研究することが付帯条件だったから。また、当時通信理論の限界を感じ始めており、新たな分野に取り組むちょうどいいチャンスとも考えた。講師になって(1年後には助教授に昇任)自分の研究室を立ち上げたとはいえ、専門の転換を行っているのだから、最初は右も左もわからないことだらけだった。特に実験はそうであった。そんな荒川を助けたのが、隣の研究室にいた、若き日の榊裕之(当時助教授、東京大学名誉教授、豊田工業大学前学長で、現在同常務理事)だった。比較的年齢も近く、名古屋という同郷であり、学者家系というところまで似ていた。どんなアプローチで半導体レーザに取り組むかに悩みながら自分の研究室を立ち上げていた荒川は、低次元半導体電子デバイスの研究をしていた榊の実験室にも出入りする。
当時、産業界ではエレクトロニクス産業が隆盛を極めており、その中核デバイスである半導体については、さまざまな分野の学者・研究者が研究開発にしのぎを削っていた。さらに時代は光通信の成長期にあり、半導体レーザは常温連続発振から10年を経てその進化が加速し、光通信をはじめとする産業セクターへの応用が期待されていた。当然半導体レーザ自体の研究先駆者も綺羅星の如くいた。
榊は当時半導体薄膜の電気伝導や量子細線トランジスタの研究を行っていたが、それに刺激を受け、荒川は「量子効果と半導体レーザを結びつけるとどんなことができるのか」という問題意識にたどり着く。荒川と榊はそこから「究極的に三次元的に電子を閉じ込めた半導体レーザはどのような特性を持つか」とイメージを詰めていった。
そして1981年、荒川は三次元量子閉じ込め構造を持つ立体ヘテロ構造の図を小さな箱として描き出し、これをアメリカの物理ジャーナル「APL=Applied Physics Letters」に投稿。翌年、その概念とレーザ応用の論文が発行される。世界で初めて「量子ドット」ならびに「量子ドットレーザ」の構造が世に提案された瞬間であり、その後の40年近く続く量子ドットという物理領域を切り拓いた瞬間でもあった。
荒川は、その構造を当初「多次元量子井戸」、1年後には「量子箱」と命名したが、しかし実際には箱型ではなく半球状や角錐の形を形成したため、やがて「量子ドット」として定着していく。人工でつくられる原子ということから「人工原子」とも呼ばれるようにもなった。
荒川らが提案した量子ドットレーザは、固体レーザと半導体レーザの長所を有し、従来の半導体レーザに比べ温度安定、小型、大量生産など大きなメリットを享受できる。実現までの道のりは遠いが、予てより描いていた量子力学の技術応用が加速すると期待した。
「半分は机上の空論」が一気に現実化
だが、学界の反応は冷ややかだった。それどころか非難すら受けた。「単なる計算でしょう。そんな、3次元的な人工構造が半導体で安定に存在するはずがない」と。
当の荒川自身も、「頭で描いた究極の構造だから半分は机上の空論。本当に実現できるかは疑わしい」と思っていた。
しかし、3年後の1985年にフランスの国立電信電話研究センター=CNETの研究グループによって、自己形成法であるS−Kモードで量子ドットの形成が確認されると、学界の風向きは変わった。荒川は研究にドライブをかける。
量子ドットの結晶成長技術と光物性の探究を進め、量子細線・ドット形成・物理(1992年)、共振器ポラリトン効果発見(1992年)などのブレークスルーを次々と起こした。
21世紀目前の1998年には量子ドットレーザのデバイス物理の基礎となる「量子ドットの連続状態」を見つけ出す。
研究所からカーブアウト
量子ドットレーザを市場化
そして2004年、東京大学と富士通研究所との共同研究により、温度安定性の優れた実用レベルの量子ドットレーザ「1.3μm温度無依存量子ドットレーザ」が誕生する。
さらに2006年には、量子ドットレーザの製造、実装を目指した富士通のカーブアウトベンチャー「株式会社QDレーザ」が発足した。
同社の量子ドットレーザは、電子エネルギーの完全離散性という量子力学の論理を利用した初めての半導体量子学素子で、摂氏220度まで安定して作動するため、プラント、自動車、砂漠など過酷な条件でも使用できる。
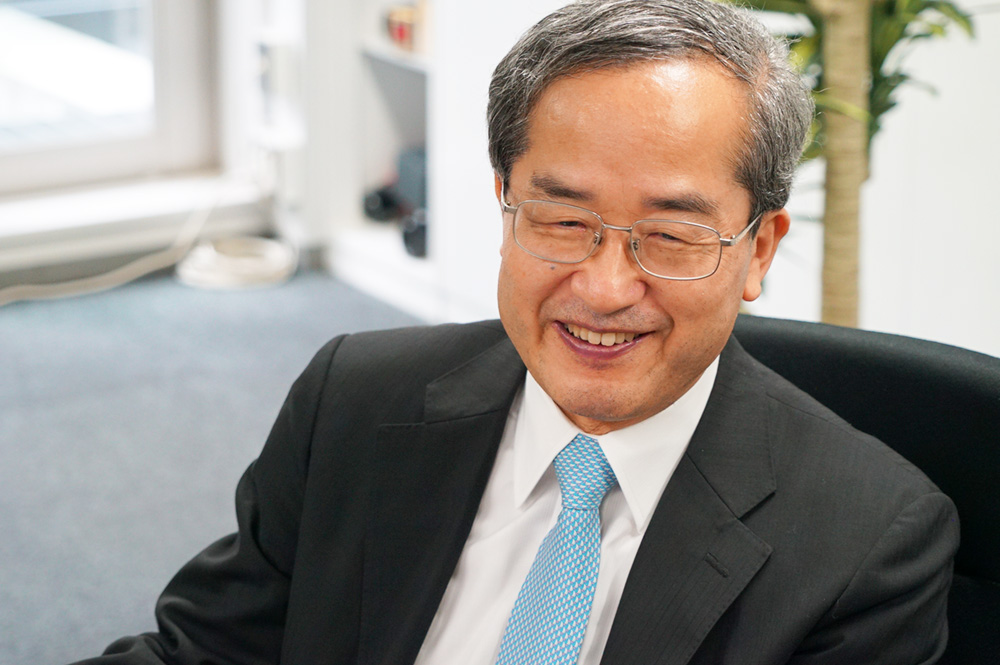
荒川は量子ドットレーザの周辺領域の研究開発も積極的に進めていた。1992年に量子電気力学に立脚した半導体共振器における強結合状態の発見、2002年頃から量子ドット・フォトニック結晶結合系の研究や単一光子発生素子の研究、2011年に量子ドット太陽電池、遠赤外線センサなどの研究にも取り組んだ。
一方で素子としての量子ドットレーザはさらに進化を遂げた。2010年には、1個の人工原子でレーザ光のもとになる光をつくりだす半導体素子「単一人工原子レーザ」を実現する。単一人工原子レーザは、エネルギー効率を劇的に改善し、ワンチップスーパーコンピュータの実現に道を拓く基礎研究と位置付けられる。
QDレーザの量子ドットレーザチップの出荷量は年間100万台を突破した。光通信用のみならず、光インターコネクト用レーザとしても市場に供給している。近年は「RETISSA」ブランドで視覚障害者向けの視覚補正アイウエアも発売している。
約40年前に荒川がゼロから挑んだ半導体レーザ研究は、世界初のエネルギーの完全離散性にもとづく半導体量子力学素子を生み、量子ドットレーザという市場を獲得し、世界のモノづくりの可能性を大きく引き上げた。
さらに量子ドットは、電子、光子、スピン、フォノンの制御に適した半導体ナノ構造であるため、量子通信、量子コンピューター、量子計測・センシングなど、量子ICTへの応用に期待がかかる。
荒川は2017年、これら一連の研究と成果に対して、日本学士院から日本学士院賞を授与された。
現在荒川は、社会実装に向けた量子計測・センシング技術にもプログラムディレクターとして関与し、その応用領域を広げるためのタクトを振っている。
量子コンピュータは長い富士山登山
量子計測・センシングは八ヶ岳登山
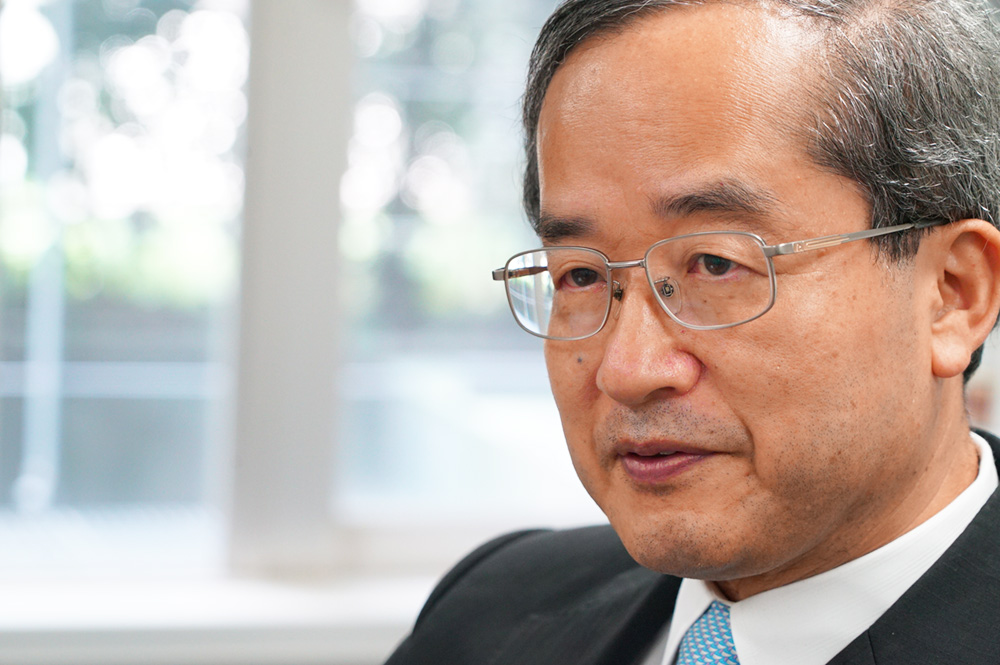
―量子計測・センシング分野の対象は多岐にわたる。各技術の研究フェーズは、現在どのようになっているのか。社会実装までのロードマップを説明してほしい。
量子コンピュータの場合、最後は誤り訂正型ゲート式量子コンピュータとなっていくことを皆が信じている。富士山にひたすら登っていくようなもので、その到達が2050年とされている。ただ、目標ははっきりしているが、どういうルートで登るかが分からない。あるいはどういう登り方をするかが判然としない。今、まだ2合目あたりの段階だ。
一方で量子計測・センシングの場合は、八ヶ岳のようなものでいろいろ、魅力的な山がある。そういう意味で内閣府の統合イノベーション戦略を見ても、量子計測の場合には固体量子センサ、光格子時計、量子慣性センサ、量子もつれ光センサ等々、個別にロードマップがあり、皆が独立している。
量子コンピュータの場合も、もちろん幾つかに分かれてマップが描かれているが、皆が関連している。量子計測・センシングも元に流れているのが量子力学ということで共通しているわけであるが、実際の展開においては非常に個別性が強い分野である。
そういう中で、既に社会実装に向けて形が見え始めてきている分野を幾つか有するのが量子計測の分野だ。
例えば光格子時計は東京大学の香取秀俊先生が世界の先頭を切ってやっており、10の−18乗の精度の技術が確立している。長年の研究に立脚して今は小型化を狙っている。光格子時計は比較的早く、5年後にはある形で社会実装として展開されると思う。
東京工業大学の上妻幹旺先生が取り組む量子慣性センサへの期待も大きい。イオンを使うか中性原子を使うかはともかくとして、原子波干渉を使って一種のリング共振器を形成することにより、加速度センサを作る。現時点でどこまで達成されたか明らかにされていないが、今後の展開が楽しみである。
今、2つの例を出したが、量子コンピュータの20年、30年先の話と比べると早い段階で、実際の応用が出てくる可能性があるし、世の中の期待も大きい。
―だいたい何年ぐらいに出てくるのか。
10年以内には光格子時計以外の量子技術でも何か出てくると思うし、出て来るべきだ。一方、ダイヤモンドNVセンターなどの固体量子センサの開発も、世界的に非常に競争が激しいが、これについてもさまざまな取り組みが行われている。わが国では、Q-LEAPで東京工業大学の波多野睦子先生が「固体量子センサプロジェクト」を推進している。基礎研究も含むが、特に産業応用に力を入れており、期待も大きい。5ピコテスラの交流磁場感度を当面の目標にし、それを超すと自動車のバッテリーのモニターにも使えるというようなものもある。もう少し先に行けば、脳磁場のマッピング(MEG=Magnetoencephalography)に非常に有効となってくる。それを使って、逆に自動車運転中の人間の脳活動をモニターするというような、夢のような話も出ている。10年後には社会実装の見通しをつけることを期待して、予算投入しているところだ。
よく言われることだが、量子コンピュータ技術の進歩は、もしかしたらこの先少し停滞する可能性もある。その時でも、量子計測・センシングや量子通信の分野の幾つかの展開が盛り上がっていれば、量子技術全体の勢いは維持されていくことになる。これにより、人材・予算・産業はあるレベル以上に維持できる状況が生まれるのではないかと思う。もちろん、量子コンピュータ技術の停滞はないことを期待する。
量子技術の社会実装という観点では、量子計測・センシングの分野は今後非常に重要な役割を果たしていく。だからこそ、今、いろいろな資金投入をしているわけである。
―計測にいる方は、「自分たちは八ヶ岳を登るのだ」といった、量子コンピュータとは違うという感覚を自覚しているのか。
八ヶ岳も立派な高山だ。だからそれぞれの中で競争しながら登っている。量子コンピュータでは、ある意味で皆さんが同じ山に登っている。しかし八ヶ岳の場合には、この研究者はこちら、この研究者はこちらと、皆が勝手に登っているところがある。例えば、光格子時計は香取先生、ダイヤモンド量子センサは波多野睦子先生、量子もつれ光センサは京都大学の竹内繁樹先生、量子慣性センサは上妻幹旺先生、と、それぞれが仲間と一緒に自分の山を登っている。では香取先生がダイヤモンド量子センサに手を出すかといったら、多分出さない。個別性が強いから八ヶ岳なのだ。
それに対して量子コンピュータは、特にソフトウエアでは皆が一緒なので議論もしないといけないし、横で誰が登っているかということ自体に関心がある。あるいはそれが自然に横にいても見えているという状況ではないか。
とはいっても、ハードウェアもしくは素子の階層では、量子ビットの話だけでも、超伝導、イオントラップ、半導体、光など多くの候補がある。傾向としてハードウエアになればなるほど量子コンピュータでも小型八ヶ岳になる。お互いが関心を持ってはいるが、自分で別の手法に取り組もうとすることはしないだろう。自分の量子ビットの開発に真剣に取り組むので精一杯のはずだ。ハードウエアはそれくらい難しい。ただし、別々のルートを登っていてもいつのまにか合流することもある。
物理の深い理解に基づくシステムであるハードウエアについては、それぞれの山を登っている代表的な研究者が日本で数人いて、それと相似的に世界で同じような研究者が同じ山を登っている。むしろ、そこと連携したり、ライバルであったりしているわけである。
―先生は昨年、政府のムーンショット計画で2050年までの目標の中で量子ICTについて発表している。周囲の反応はどうか。また政府関係者が量子ICTにどの程度期待しているのか。

昨年の場ではムーンショットの目標をどこに設定するかということが1つあった。当然、われわれのワーキンググループは、量子コンピュータに設定することが大体決まっている中での議論だった。
歴史を振り返ると量子力学はほぼ100年前に確立した。シュレーディンガー、ディラック、アインシュタイン、ハイゼンベルクらだ。いまの半導体技術もこの量子力学に基づいている。そもそも半導体を生み出したバンドギャップというものは、量子力学そのものである。そこからいろいろな発展がなされた。トランジスタやレーザも量子力学をベースにしている。よく「量子0」や「量子1.0」と言っているが。私もレーザなどをやっていた。
そういう中で2000年ごろから、もつれ状態の生成や制御技術などが、だんだん本格的に発展してきた。
量子コンピュータの研究も「ショアのアルゴリズム」が1994年に出てきて、一時盛り上がった。それが少し落ちて細々とやっていた。東京大学の中村泰信先生も落ち着いて研究をやっていたのではないか。それが東京工業大学の西森秀稔先生らによる量子アニーリング方式にもとづいた「D-Wave」コンピュータの出現を契機に状況が変わった。そこから全体に盛り上がってきた。
そういう中で、ムーンショットのテーマの一つをどうするかということになった。ムーンショットだから、ずっと先の話をターゲットにしようと考えた。そういう意味で誤り訂正型ゲート式量子コンピュータはちょうどいいのではないかということで意見がまとまった。相当難しくて、相当期間が長く、しかし実現不可能ではない、社会貢献もある、まさにムーンショット的なチャレンジといえる。
誰もが、10年ではできないだろう、ただ25年ぐらいだったらできるかもしれないというような思いをする中で、ちょうどそのころに量子超越性の話がGoogleから出てきて、大きな火が点いてさらに元気になった。Googleが実現したからすぐというわけではないものの、第何次か分からないが、今、量子コンピュータのブームが来ているといえる。
過去の大きく開花した先端技術の発展史をみると、大体は何回かオシレート(振り子状反復)している。1回落ちるが、また少しずつ上がっていき、振動を繰り返しいつか成功という水面から頭を出す。その時期が量子コンピュータの場合には、2050年ぐらいではないかと考えている。世界中が取り組むテーマとしては、非常に意義があるテーマであり、国家目標として設定する価値もあるとワーキンググループは結論付けた。
量子コンピュータ研究は
既存の汎用コンピュータ技術のレベルも引き上げる
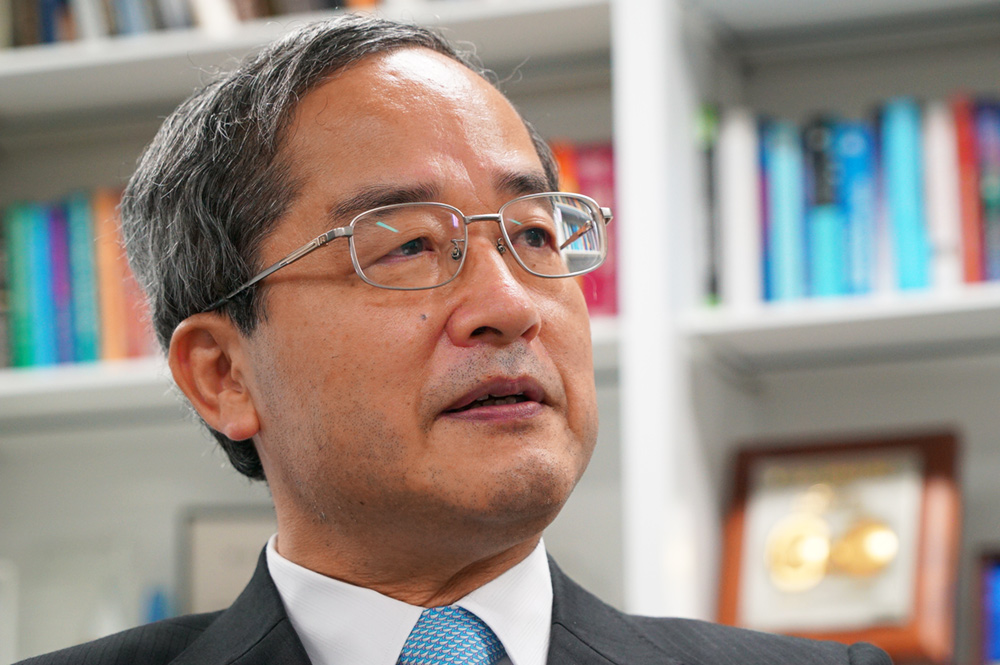
―今は、役人をはじめ産業界などの期待値はかなり高い状態なのか。
高いと思う。政府では有能かつ熱意ある役人がこの分野の支援に取り組んでくれている。欧州の予算は1,000億円、米国も2,000億円、中国も同じくらい、日本は50億円ぐらいと役人は言う。そこで日本は後れを取ってはいけないと上手にアピールする。どんどん増えてきて今年度は350~400億円となった。ただし、欧州の1,000億円というのは、10年というスケールで、また、人件費やオーバーヘッドも全部入った数字だ。だから、もはや実際の差はそれほど大きくない状況にあるのかもしれない。今後は、広義の量子技術分野の研究開発や人材育成にも、支援を拡大していくことが望まれる。
かつては半導体産業やその応用産業で夢を描きながら、若い人たちがエレクトロニクス分野に入っていった。それが途絶えてきている状況の中で、この量子技術が、歴史的に量子力学の第2世代もしくは第3世代として、2か3は定義によるが、新たな産業として発展する期待感がある。
学術的な発展の夢、産業的な発展の夢、計算能力が上がる結果による社会への貢献、そういう夢がちょうどいい形で出会い、ぞれぞれマッチングした状況に今はなっている。波及効果も極めて大きい。
コンピュータ技術全体の観点からいえば、量子コンピュータの能力を上げて社会実装を実現しようという努力は当然行うわけであるが、2050年まで待つことはできない。なので、今の「富岳」のように汎用コンピュータそのものの能力を上げないといけない。汎用コンピュータの能力を上げれば、量子コンピュータのエミュレート、あるいはシミュレートすることができ、両方の相乗効果が出てくる。必要に応じて、システム全体は古典コンピュータだがプラグインで一部量子コンピュータというようなハイブリッドの計算機もありえる。そういう機運が全体に出てきたということだ。
それから若い人たちにも刺激になっている。理工系か、医学部へ行くかとなった時に、コロナ禍の様子を見ていると医者は大変、ということになるかもしれない。そこで量子ICTが興隆すれば、量子ICTをやりたいという若者が増える可能性がある。しかも量子ICTを勉強することは、それ自体の専門性を深めるだけでなく、つぶしが利く。量子コンピュータの理解があれば、いろいろなシミュレーションができるので、例えば金融の解析もできる。幅広く人材を供給できる可能性を持つ分野として量子ICTがある。
単に量子コンピュータのみではなく、そこから出る人材的・産業的な広がりや、汎用コンピュータや通信など既存の技術にも大きな影響を与える。
―ゲート型量子コンピュータの実現に至るまで期待できるスピンオフは、どのようなものがあるか。
ムーンショットの時にもだいぶ議論した。よく言うのは、量子誤り訂正などの手法を使うと、MRI(核磁気共鳴画像)の超偏極や量子計測にも役に立つ。また、量子コンピュータは、最後にいろいろなネットワークが組まれることになる。そうすると量子ネットワークが必要である。量子ネットワークはQKDのネットワーク化にも役に立つから、そういったところに波及していくだろう。それは誤り訂正型ゲート式量子コンピュータそのものよりも、ずっと早く実現するだろう。
また、前述したように既存の汎用コンピュータに対するインパクトだ。波及効果は常にあり続ける。「量子インスパイア」とよくいわれるが、量子コンピュータで考えられたアルゴリズムが、古典コンピュータで使われるようになる。量子アニーリング方式がその例だ。
―論文の引用数を比較すると、日本の研究開発の遅れが気になる。中国が増え、アメリカやヨーロッパも微増している一方で、日本は落ちている。どう認識しているのか。
じつはこれがよくわからない。理由として一つ思うのは、欧米は日本に比べて国際共同研究が非常に盛んだから、共著論文が多いことだ。中国とも共著論文が多い。中国本体の論文が増えているので、そこと一緒にやっていると欧米の論文数も増える。もちろん、統計では、共著論文の場合、国の数できちんと正規化している。それであっても欧米の論文数が微増状態にあるのは、多分、国際共同研究の効果が出ていると想像する。
もう一つは、大きいプロジェクトをやり始めると、目的型研究の側面が強くなってくるため、だんだん論文が書きにくくなってくることだ。また、インパクトファクターが高いものに投稿しがちだ。小さな論文を書くよりも、予算が安定しているから、大きいものを狙ってくる。それ自体悪いことではないが、査読で拒絶されたときに次のレベルの雑誌に投稿する。そんなことを繰り返すと出版までに時間がかかってしまう。そういうこともあるかもしれない。
Googleがなぜ莫大な金をつぎ込んで
量子コンピュータを開発するのか
―量子ICTのなかで旗振り役となる人物や団体がいないと、米中欧のパワーゲームに翻弄されないか。日本がプレゼンスを発揮していけるのか、中心にいる先生方は、どのように捉えているのか。
本来は、学術的オリジナリティを有して尊敬を集める人がリーダーである。ただ、実情は多様である。Googleのような企業組織が引っ張ることもある。リーダーには、学術のリーダー、推進のリーダー、社会実装のリーダーもいる。リーダーの姿が多様になってきている時代ではないかと思う。
国を動かしていく、あるいはよりグローバルに見た時に、量子コンピュータ分野全体の担い手は最終的には投資家かもしれない。
Googleなどがなぜ量子超越を実現できたかというと本業で大変儲かっているから。彼らからすれば、量子コンピュータで成功すれば株価が上がる。R&Dに1兆円掛けたとしても、株価が少し上がるだけで元がとれる。そこに彼らのビジネスモデルがあるわけだ。そのビジネスモデルと技術開発が、いい形で合金化されると、ものすごく世界が動く可能性がある。それをどのような形で呼び込むかというのは、答えはない。国全体では、旗振り役が政治家であってもいい。投資家と上手に組む学術的オリジナリティを有する研究者がリーダーとなるのが理想だが。
量子コンピュータ開発はマラソン
トップに立つには先頭集団にいることが大事だ
―日本が基礎研究で先行していたのに、産業化の段階で他国に後れをとってしまった先進技術例はたくさんある。量子ICTにおいても二の舞になる懸念はないか。
私はよく量子コンピュータの研究をマラソンに喩える。25年先のゴールに向けては先頭集団にいるべきだと。今の時点で別にトップを走っている必要はないが、あまり後ろにいたら話にならない。先頭集団で走りながら、最後に近いところでいかにトップに行くかということが重要だ。その戦略を誰がどうつくっていくのか。
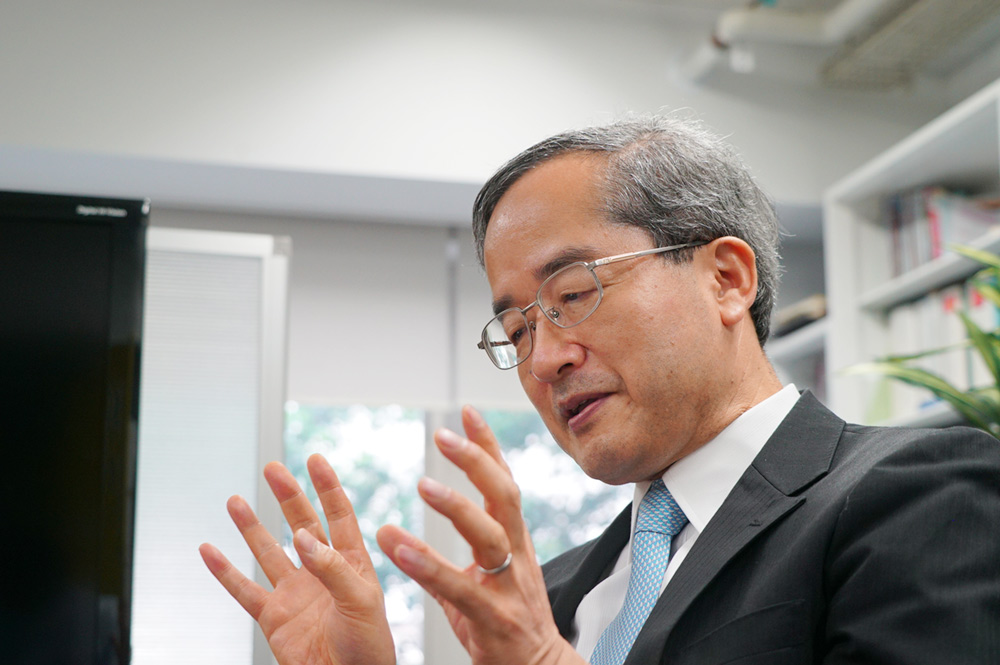
25年先というのは本当に分からない。その時に量子コンピュータのトップ集団にいながら、最後にどう出るかということである。もちろん、走る中でいろいろな波及効果はあるから他の産業もバイプロダクトとして育つ。ただそれはまた別の話だ。本命については、ほどほどに走っていればいいという気がする。いろいろな方式があって、どれがいいかまだ分からないから。
むしろ息切れをしないということが重要だ。皆がファンディングをやめてしまったら、本当に大変なことになる。過剰な夢を持たないことも重要かもしれない。産業界でも長期的量子技術開発とそのビジネス戦略がきちんと継続される仕組みをつくっておくということも必要。
投資を呼び込めるビジネスモデルを創出するのが
量子ICTフォーラムの役割
―2050年までのムーンショットの道程で、量子ICTフォーラムをしっかり機能させるために必要なことはなにか。
やはり量子ICTフォーラムがよりオープンイノベーションに向けて広く活動することに意味があると考える。
多分、2つの側面がある。一つはQKDを本当に実現するための中核としてのフォーラムをいかにまっすぐ伸ばすかということだ。
それに対して、幹の幅を広げることも重要だ。量子技術全体を次第に包含していくような状況がフォーラムの中にさらに生まれくるといいと思う。
幹が広がり、さらにこのフォーラムが求心力を持つためには、関わる人たちの活動を支える資金力が必要である。要は投資だ。国の投資か。産業界の投資か。あるいは別の投資でもいい。そういうものを呼び込めるように発展していくことが重要である。
―産学官連携でお金をどう入れるのかという点で、役割としてある種の接着剤的な機能をフォーラムが担うようなことになってくるのか。
そういう役割を果たせればいい。従来のように官主導でフォーラムをつくって、やや受け身的な組織で運営をしていくだけでは不十分である。今のように世界がダイナミックに変化する中で、しかもいろいろな分野が量子技術として広がる中で、量子ICTフォーラムの方向性を考えることが大変重要だ。現状の課題を整理し乗り越え、発展させることができるかどうか、広い意味でのビジネスモデルを創造できるかが量子ICTフォーラムの命運を決める。
―量子ICTフォーラムは新しい産学官連携のビジネスモデルの構築とそれにふさわしい人材育成も担うことになる。
成功したあるビジネスモデルに倣って、他の人が同じことをやってもビジネスは成功しない。新しいモデルによる新しい形のフォーラムを自ら創るという覚悟が、今問われている。
人材育成については、いくつかの大学が今一生懸命取り組み出しており、いろいろな人材育成の拠点もできる。そことどのようにアライアンスを組むかということも、重要と思われる。
1つ尖ったものが成功すれば、皆が寄って来て、それでますます発展していく。そういうポジティブなスパイラルに持っていきたい。それが先に述べたビジネスモデルであり、量子ICTフォーラムだから初めてできるようなものを考えることは意義深い。
昔、産学協同は悪だとまで言われていた。大会社は自前の中央研究所を持ち、基礎研究は企業でやるから大学は教育だけして学生を送ってくれと言っていた。ところが1990年代に入り、さらには2000年代になるとその余裕がなくなり、大学が企業の基礎研究所の役割を果たすことが期待されるようになった。そこから十数年。いまは大会社も未来の輪郭を描きにくくなりつつあるようだ。この間、色々な出自のベンチャー企業が出てきた。大学発もあるし、企業からスピンアウトするものもある。社会全体が複雑化しグローバル環境となった今日、連携のベストチームをどう作るのかを、企業・大学・国立研究開発法人・国は本気で考えていく時代になっている。
ノーベル物理学賞のメダルには、ラテン文学の最大傑作であるウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』6巻の一節がアレンジされた碑文がある。「Inventas vitam iuvat excoluisse per artes」。原文では、祖国のために戦った勇士や潔い生涯を終えた神官とともに、祝福された者のみが住む月桂樹の茂る丘の住人として「真理の発見に高潔な人生を捧げた人たち」(小野塚友吉訳)と紹介されている。未来を覗き見ることはできない。ただ、そう遠くないうちに、量子ICTの分野でめざましい功績をあげた者がその栄誉に浴する日がくるだろう。これは臆面がない話だが、その栄誉を日本人からも、と願いたい。連携のベストチームをどう作っていくのか。量子ICTフォーラムが振るうタクトに期待したい。(取材:加藤俊 /撮影:古寺正樹)
