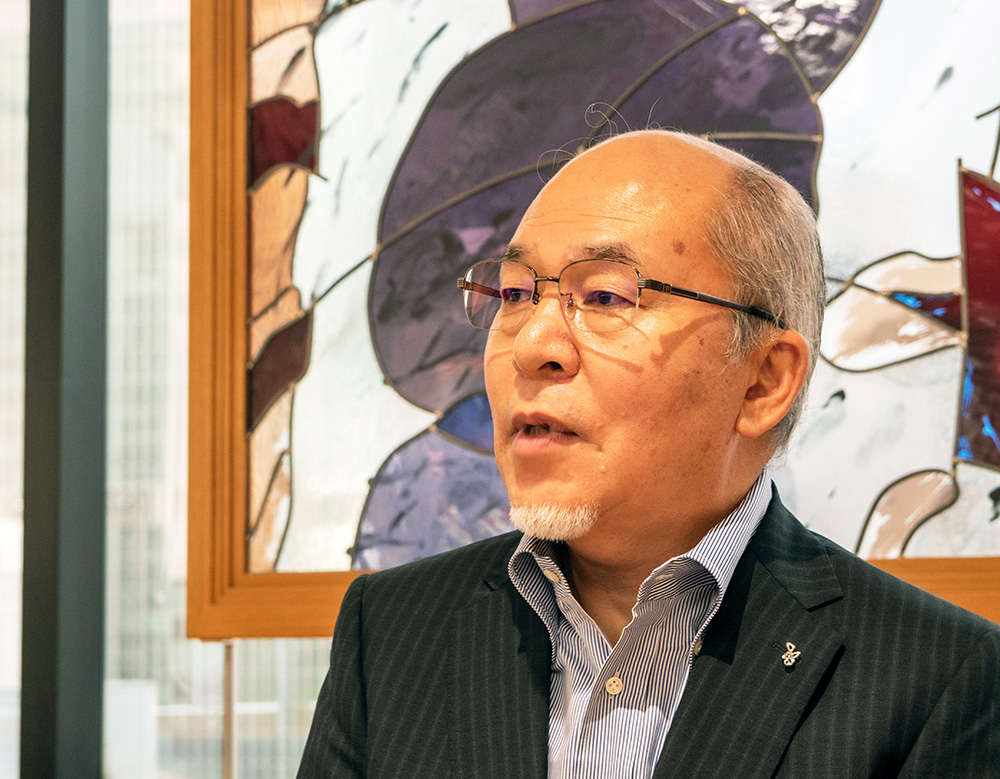「いつまで砂糖水を売り続けるつもりだ。一緒に世界を変えたくないのか」――。
1983年、アップル(Apple)の創業者、故スティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)はある男にこう迫る。
ある男とはジョン・スカリー(John Scully)。飲料水メーカーの巨人、ペプシコ(PepsiCo)の社長だ。ペプシコは常に業界トップのコカ・コーラ(Coca-Cola)の後を追いかける立場だったが、スカリーはそのコカ・コーラを捉えた。
一方当時のアップルはまだ代名詞となるパーソナルコンピュータ、マッキントッシュ(Macintosh)を発売する前で、ジョブズは世界を変えるためには、商品の機能や魅力だけではなく、グローバル企業としてのマーケティング力とマネジメント力を必要としていた。白羽の矢を立てた相手がスカリーだった。ジョブズは18ヵ月に渡ってスカリーを口説き続けた。
しびれを切らしたジョブズが放った言葉が冒頭のセリフだ。いかにアップルが勢いのある企業だとしても、自社の主力商品を“砂糖水”とまで言われて、スカリーの心中はもちろん穏やかではなかったはずだ。しかもジョブズは一回り以上も年下だ。だがスカリーはこの激越なオファーを受ける。
翌年アップルはマッキントッシュを世界に送り出す。しかし強気の予測で在庫が溜まり、アップルは創業以来初の赤字決算となった。スカリーはその原因をつくったのはジョブズと考え、役員会にかけた。役員は誰もジョブズの味方をしなかった。軒先を貸して母屋を取られた形となったジョブズは、立ち去るしかなかった。
確かにジョブズの振る舞いはどこか狂っていた。ある日は神のごとく人を絶賛し、翌日はその人物を完膚なきまでにコキおろした。天使と悪魔が共存している奇人−−。だがそんな彼を認めていたのは周りの技術者たちだった。
マーケティングとマネジメントを優先させ、時に政治にも秋波を送るスカリーにエンジニアたちは愛想を尽かし、ひとり、またひとりと去っていった。去ったエンジニアが向かったのは、ジョブズの立ち上げたスタートアップ「ネクスト(NeXT)」社でもあったが、多くはカリフォルニアの北に向かった。もう1つのライジングサン、マイクロソフト(Microsoft)である。
一方スカリーのアップルは長くは続かず、低迷に陥り、1993 年、スカリーはアップルを後にする。スカリーが退去して3年後、ジョブズはアップルに復帰する。その後の快進撃は周知の通り。ただその快進撃はジョブズの情熱だけではなし得なかった。ジョブズが去った後もアップルらしさを求め、独自に研究開発に取り組んでいたエンジニアがいたからこそ、だった。
この一級のシリコンバレーのドラマを間近で見ていたのが飯塚だった。
(取材・文・撮影:佐藤さとる)
20世紀末のIT興亡史の主役たちと直に交流
飯塚は当時NTTの技術評価部門長としてアメリカのAT&T(エーティ・アンド・ティ)やアップル、シリコン・グラフィックス(Silicon Graphics International)、マイクロソフトなど世界のIT史に名を連ねる巨人、ベンチャーに足を運んでいた。マイクロソフトのビル・ゲイツ(William Henry Gates)とはプロバイダ事業を行う交渉を詰めたこともある。米国を代表する映画監督ジョージ・ルーカス(Georgi Walton Lucs)と交流し、CG映像の可能性を探り、紹介されたシリコン・グラフィックスやネットスケープ(Netscape)の創業者、ジム・クラーク(Jim Clarke)とアライアンスの可能性を語った。
「アップルが復活したのは、ジョブズが戻ってきてからだけど、なぜ一気にiPodやiPhoneなどが続々生まれたかというと、ジョブズがいったん去ってからもこうした開発を脈々とやっていたエンジニアがいたからだと思う。たぶんスカリーから止めろと言われていたはず。だけど隠れて続けていた。トップが引いたとしても、情熱をもってやり続けるエンジニアがアメリカにもちゃんといるんだと思って、僕は感動した」
飯塚が技術評価部門長として日米を往来していた時は、アメリカの通信やコンピュータ業界が東海岸から西海岸にシフトしていた頃だった。それは同時に電子立国として世界の羨望を集めていた日本の電子産業が、その足元を揺さぶれられはじめた時期でもあった。
実際日本の電子産業は2000年に26兆円のピークを迎えると2015年には半分以下の12兆円まで落ち込んでいる。
民営分割交渉人、飯塚久夫
飯塚は1972年に日本電信電話公社に入社し、事業部門で次世代ネットワークの開発・導入に関わってきたが、83年から郵政省と民営分割の交渉の場にも立っている。公社の民営化は、アメリカの通信自由化で通信の巨人AT&Tが分割されたことを受けての政策だった。アメリカのUSTR(合衆国通商代表部)はAT&Tに倣い、NTTも分割しろと要求してきたが、飯塚は「日本はカリフォルニア1州ほどの面積と人口。それを分割する必要はないでしょう」と論じた。
飯塚は、リストラクチャリングの実務に長けていた。民営化するには、電気事業通信法を書き換えなければならない。民営化の法案作成を手伝い、当時の郵政省と3年をかけて詰めた。
こうして実現した電電公社の民営化は、各社の競争を促すことで体力をつけることにあったが、実体はそうならなかった。NTTと付き合いのあるICTベンダーは、大口の得意先としてのNTTに頼っていた。
「各社は決して開発を怠っていたわけではない。熾烈な共同開発をやっていました。NTTの研究所を挙げて、メーカーの研究所と共同してアメリカに負けない製品をつくっていた。ただメーカーの中央研究所が2000年頃を境にどんどん廃止されていった。次第に中央研究所は金食い虫だと考える経営者も出てくるようになってしまった」
貿易摩擦のトラウマに取り憑かれた日本ICT企業
ただ飯塚は少し経営者の弁護もする。日本は80年代から続く貿易摩擦に臆病になっていた、と。
「とんでもない政治的圧力がかかったトラウマがあって、新しいことに挑戦しにくい体質になっていった」。抵抗せず、与えられた環境のなかで工夫を凝らすことが日本企業の習い性となっていた。
片やアメリカでは、90年代からシリコンバレーを中心に電子産業はICT産業として復活していった。
日本の電子産業復活、ICTの興隆の芽はないのか――。飯塚は日本のICT企業がスケールしなければいけないと考えた。
しかし、日本の大手メーカーにその余力はなくなっていく。懸念を募らせる飯塚にある学者が「日本企業がスケールするには、業界としての合従連衡が必要」と語った。だがこの空気を読み、実行するICT企業は少なかった。
「一部半導体関係で合従連衡を行ったが、それでも遅かったと思う」と悔しさをにじませる。
論文数が急増。官民が潤沢に研究に投資するドイツ
科学技術は人類をまだ見ぬ明日へ導く共有資産だが、近年は技術ナショナリズムが風に煽られた燎原の火の如く世界を覆っている。現代国家にとって技術の主導権はすなわちその国の未来を約束するからだ。
そのためには産と学はもとより、国の研究機関、官庁が連携をする必要がある。
目に見える効果を上げているのは、インダストリー4.0を掲げるドイツだ。
ドイツは今世紀に入ってから政府からも民間からも研究のために豊富な資金を投入している。そして投じられた資金は、確実に結果を生んでいる。
たとえば研究論文。TOP10%の補正論文数が増加し、2000年頃に年間5000本だった年間7500本以上にまで増えた。対して逆に日本の論文数は2000年代に入ると頭打ちとなっている。2016年段階では4000本を割っている。
飯塚はドイツが研究論文数を増やしているのは、“程よいガバナンス”が効いているからだと見る。
ドイツには、基礎研究を軸にした研究機関と応用研究を行う研究ユニットがそれぞれ国内に80ずつある。前者が「マックスプランク学術振興協会」、後者が「ブラウンフォーファー応用研究促進協会」の所属だ。つまり研究内容で余計な競合がないため、研究予算が有効に使えるのだ。また研究の輪郭が見えやすいため連携もしやすい。
飯塚が感心したのは、研究所と産業界の人員交流が非常に盛んであることだ。研究所の研究者がそのレベルを保つために大学教授を兼任することもある。人の交流が情報の交流を生み、議論が活性化する。
「よき産官学連携そのものだ」と飯塚は唸る。
「日本はドイツのように前向きな産官学連携ではなく、否が応でも“やらざるを得ない”状況にいる。
食料や資源のない日本が世界に発展できたのは取りも直さず、科学技術の力。そのなかでも得意としてきた電子技術が凋落するというのは、本当に堪らない。
日本の電子産業が衰退した一因として中央研究所の廃止があると言ったが、ではそこの研究員はどこに行ったかというと、大学や国の研究機関。そこで素晴らしい研究成果を上げている人がたくさんいるんですよ」

飯塚はそこに科学技術立国日本の可能性を再び見出している。
そういった力のある研究者と産業界、国が一体となって「よき産官学連携」の1番のモデルになりうるのは、量子の世界だと飯塚は見ているのだ。
「量子ICTフォーラムに参画してびっくりしたのが、企業の中央研究所にいた先生方・研究者の方がたくさんおられたこと。本当に世界の研究者が目を瞠るような成果を、どんどん出してる方がたくさんいらっしゃる。そこに新しい発想の若手の方が入っていただく。この量子ICTフォーラムがその機能を果たすことになれば、本当に素晴らしい」
 日本とドイツの研究費の推移。政府系投資もさることながら、民間企業の投資の高さが際立っている。(出典:豊田長康「科学立国の危機」[東洋経済新報社]
日本とドイツの研究費の推移。政府系投資もさることながら、民間企業の投資の高さが際立っている。(出典:豊田長康「科学立国の危機」[東洋経済新報社]
アルゼンチンタンゴに魅せられた中学生
飯塚が「少しでもお手伝いできれば」と量子ICTフォーラムの発展に心血を注ぐのは、電子立国の衰退を肌身で実感してきたこともあるが、大学時代に量子物理学の世界に関心を持ったことも大きい。
しかし飯塚は訳あって、実際には大学で音響工学を選んだ。
その原点は中学時代の自宅にあったラジオだった。当時から「マイナー好き」を自称していた飯塚は、周囲の同級生がビートルズやロックンロールに熱狂している姿を横目に自らはアルゼンチン・タンゴにのめり込んだ。爾来タンゴはその後の飯塚の伴走者となった。
飯塚は昔は遠慮気味だったが、今は初対面者には「日本アルゼンチン・タンゴ連盟会長」と印字された名刺も添える。
飯塚と量子力学を結びつけたものは、そのアルゼンチン・タンゴだった。
当時レコードはまだ高価で飯塚の小遣いでは買い揃えることはできなかった。代わりにラジオに耳を傾けた。飯塚はラジオなるものが、なぜ音を出すのか不思議に思っていた。目に見えない物理事象に興味をいだき、とくに電気に惹かれていく。
高校時代に突然聴覚を奪われる。音響工学を目指す
高校時代に入ると飯塚の進路はおよそ決まっていた。理学部か工学部で電気を研究することだった。その青春時代の飯塚をある日絶望が襲う。突然聴力を失ったのだ。
「高校3年だったと思うが、耳が聞こえなくなった。好きなタンゴも聞けず、もうどうしたらいいかわからなくなるほど落ち込み、絶望した」という。
幸いにも聴力は10日ほどで戻ったが、この体験は飯塚が進むべき道を確定させた。
「なぜこんな不思議なことが起こるのだろうと思った。これを研究しようと。音楽が好きだから音について勉強したい。電気も研究できる。両方勉強できるようなところを探したら、音響工学という学問があることを知った」
その研究の中心となっていたのが東北大学だった。東北大は飯塚の知的好奇心を刺激する場だった。飯塚の関心領域は広がっていく。
音の領域では音響学からさらに、音の受け手である人間の脳神経の構造、聴覚心理学なども学んだ。
西田幾多郎の哲学に量子力学の根源を見る

飯塚は哲学にものめり込んだ。東北大は総合大学であり、その学問領域の幅が広く、分厚い。理系でも教養課程でしっかり文系の科目を充実させていた。飯塚は講義とは別に哲学者のハイデガー、ヤスパース、ニーチェ、キルケゴールの著作を渉猟し、三木清、西田幾多郎の著書などを耽読した。とくに西田が唱えた「矛盾的自己同一」という思想に深い感銘を受けたという。
「振り返るとまさに量子力学の根源の思想はこうだと突きつけられた」。
こうして飯塚は量子に惹きつけられていく。しかし大学3年の時に衝撃的な知性に出会う。半導体を専門としていた西澤潤一だ。
西澤は、いつも教室に入って来る時は、手ぶらだった。コピーもメモの一片もない。そしておもむろに黒板の左上から超関数を書き始める。気がつくと関数は右下までたどり着いていた。
「左上から右下まで毎回、毎回びっしり書く。ディラック(Paul Adrien Maurice Dirac)のデルタ関数だったから、量子の最先端。圧倒されて。後にも先にもこんな先生は出会ったことはなかった。すごい先生がいるものだと思って、こりゃついていけないと諦めたんです」
飯塚は語るが、飯塚にとって量子が世界を明らかに変えることは自明だった。学部時代は物理学、情報工学を拓いた3巨人、すなわちジェームズ・クラーク・マクスウェル(James Clerk Maxwell)、ジョン・フォン・ノイマン(John von Neumann)クロード・シャノン(Claude Elwood Shannon)、の書物に感銘した。
その後飯塚は専門として選択した音響工学に没頭し、東京工業大学の大学院に進んだ。東工大は音響でも超音波の専門家が多く、飯塚は超音波も研究している。
それから時は一気に下って現在。飯塚は量子との縁を感じざるを得なかったという。量子ICTフォーラムの副代表理事である斉藤史郎が、原子力発電の高速増殖炉の異常を超音波で見つける研究をしていたとインタビューで語っていたからだ。
飯塚はかつて東京電力の委託を受けて同様の研究をしていたことがあった。同様の研究を同じ量子ICTフォーラムに身を置く斉藤が、10年後にしていたことに奇遇を感じざるをえなかった。
量子ICTフォーラムは、飯塚がたどり着くべくしてたどり着いた約束の場だった。
「よき合従連衡」の実現にふさわしい人物
飯塚は大学院修了後、その知見をよりパブリックな場で活かそうと就職先に日本電信電話公社を選んだ。以来、電子交換機や通信網の開発・計画、マルチメディア構想、インターネット事業などNTTの次代を切り開く現場に立ち続け、世界や日本の電子産業を担うベンダーと議論を交わし次世代技術開発に携わった。民営化にあたってはその当事者として、民営化後の通信業界の絵を描いた。
以降は複数の企業のトップとして実績を重ね、また母校東京工業大学の理事・副学長として次世代のサイエンティスト、エンジニアの育成にも注力した。
飯塚の強みは、産官学にネットワークをもち、技術の現在地がわかり、若い世代の育成に長じているところにある。つまり全体を俯瞰し、人と課題、知見と知識、能力と才能をつなぎ、インテグレートできることだ。
まさに「よき合従連衡」の実現にふさわしい人物なのである。

――かつて電子立国として燦然と輝いていた日本の電子産業がこれほどまでに落ち込んだ原因は、大手メーカーが中央研究所をやめてしまったことが大きいと?
「いろいろあるが、2000年頃に大手メーカーが続々中央研究所を廃止したことは大きい。これは基礎研究の軽視であり、技術に対する洞察力のある経営者が少なくなったとも言える。逆に技術と市場の将来をよく見る人間がトップになって復活したところもあるが。
海外は研究費をどんどんかけて、スケールしている。成果を出している。
2000年にそういったことを語っている学者がいた。「健全な合従連衡でスケールしていく必要がある。日本の電子産業がこんなバラバラでは絶対に世界に負ける」と。だが残念なことに日本のメーカーはよき合従連衡をしなかった。
一部、ルネサスのように半導体メーカーで起こったが、遅きに失したと思う」

――合従連衡がなされていれば、優位に立てるチャンスはあったのか。
「アメリカは1984年にAT&Tの分割とIBMの独占訴訟取り下げという戦略で情報通信の競争力が増し、見事復活した。日本もその圧力を受けてNTTが民営化(その後分割)されたけれど、競争力がつかなかった。いろいろ背景はあるが、技術に対する投資がなされて来なかったことが大きい。それはドイツなどの例を見ればわかることだ。
それ以外にもいくつか大きい問題がある。
1つは日本企業がアメリカ人の経営を読み間違っていたことだ。アメリカ型経営は短期を見ているというが、そうではない。90年代にシリコンバレーの興隆を見ればわかる。彼らは短期の利益は見ていない。その先のことを見ている。私が付き合ってきたのは、“10年後にこういう技術を実現する” “この技術を通じて世の中を変える”と考えているような連中ばかりだった。
もう1つは、アメリカは企業秘密主義が徹底しているから情報交換などはしないという誤解だ。とんでもない。ノウハウこそ話さないが、自分を高める、技術を高めるために外部の人間と積極的に彼らはディスカッションをする。
シリコンバレーに行くと、深夜までカフェやレストランでいろんな会社の人間が集まってディスカッションをバンバンしている。この現実を見誤った。
それからアメリカ人は誰にとっての技術かということを日本人より見ていると思う。
私はタンゴ好きでそれなりに音源(100年前のSPレコードから今日のCDまで)再生に気を遣っているのだが、昔AT&Tによく出入りさせてもらった時に、そこのベル研究所にあったアンプの真空管を譲ってもらったことがある。
この真空管はウエスタン・エレクトリック(Western Electric)社製の300Bという名球。ウエスタン・エレクトリックは一時期AT&Tの製造部門としてこうした電気機器もつくっていた。基本的に手作り。私は音響工学が専門だが、決してオーディオマニアではない。
御存じの通り、CDになるとアナログレコードと違って高音までしっかり出る。だから、ロックならいいかもしれないが、タンゴにはきつい。でもこの真空管で聞くと音が円やかになる。それには聴覚心理学上の理由がある。
何が言いたいかというと、どんな製品でもスペック値があって、日本人はそのスペック値を競うのだが、スペックはスペックとして、どんなに良い製品をつくったとしても、最後にユーザーである人間が喜ぶ製品になっているかが重要だということ。海外の技術者はそれを失っていない気がしている。日本製の優秀さは知っている。スペックは素晴らしく、故障しない。しかし人間にとってどう大事かという疑問符は残ってしまう」
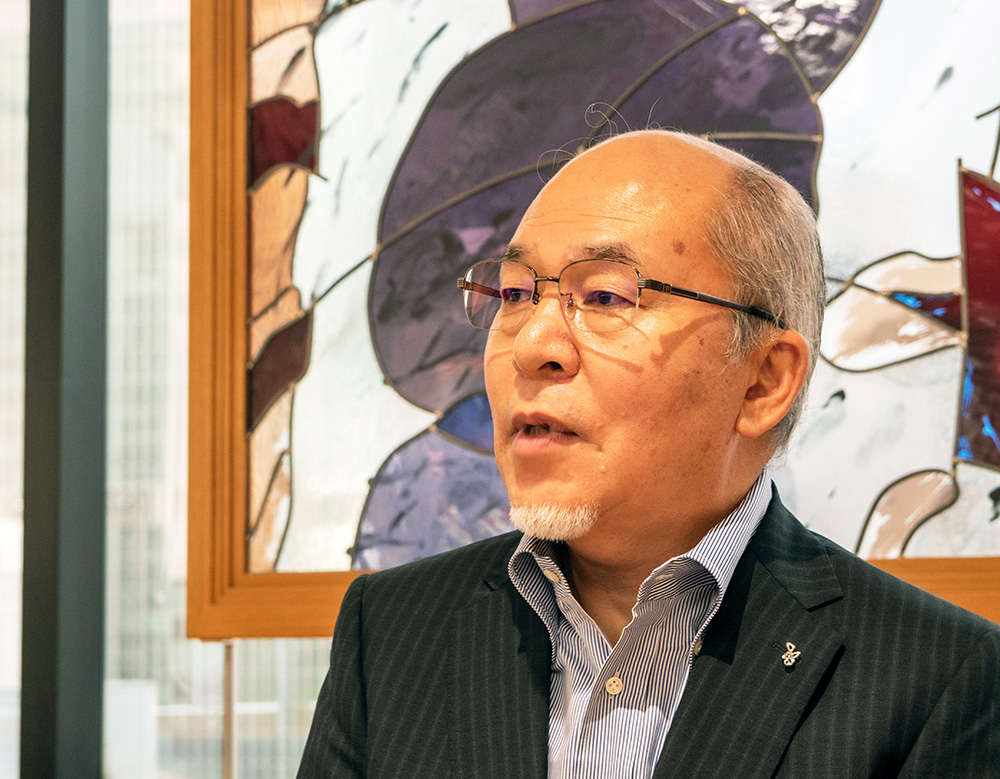
――日本の量子研究はアメリカや中国から何周も遅れているという声も聞くが、かつての電子立国のようなトップランナーに立てる道筋はあるか。
「80年代の日本の電子産業の輝きを知っている電気大好き人間としては、なんとしても日本の産業を復活させたいという思いがある。
なぜ日本が凋落したのかという原因は分かっている。やるべきことも分かっている。国もドイツなどの状況を知っているから、やるべきことの理解は進んでいるのは確かだ。ただ残念ながら中央官庁がまだバラバラなところがある。
一方でトップサイエンスの人間が、自分たちのことをPRしてこなかったことも事実だ。量子の研究者は、自分たちの研究についてほかの分野の人間に分かってもらわなくてもいいと思っているフシがある。量子に限ったことではないが、日本の研究者はそういう蛸壺的思考が強いと思っている。
そうではなくて若い世代やその親たちに、自分が生きている間にとんでもないことが起こるのだということを伝える必要がある。そういうアクションを起こさないと、世の中に広く理解されず、投資も人材も集まってこない。日本の科学技術は進展していかない。
2000年頃に中央研究所がどんどん廃止されたと話したが、そこにいた研究者はどこに行ったのかというと、幸いにも大学や国の研究所に移っていた。そういう人たちが素晴らしい研究をしているのだ。
このフォーラムに来てびっくりしたのは、そういった輝かしい研究をしている人がたくさんおられるということだ。
遅れているかどうかより、日本が量子をやるのは必然なのだ。いまのノイマン型コンピュータはアーキテクチャ的に限界が見えているから。そこに手をつけていないと量子コンピュータの時代が来た時に日本が潰れるのは目に見えている」

――改めて量子ICTフォーラムの意義について伺いたい。
「日本にはまだまだ優れた人材が学だけでなく、産にも官にもたくさんいる。そういった人たちを活かすためにも、産官学の日本らしい「よき合従連衡」を創り出し、若い才能のあるさまざまな分野の人が集まってディスカッションする場が必要だし、そういう空気をつくっていくことも重要だ。それができるのがこの量子ICTフォーラムだと考えている。そういう場にこのフォーラムがならないといけない」
――量子関係の開発は速度を増している。量子科学技術のこれからを担う、若い世代の育成も急ぐ必要がある。今どういった思いを彼ら、彼女らに伝えておきたいか。
「人間の思考は歴史の遙か過去から偉大な「変わらないもの」があり、しかし、その変わらないものの中から「変わるもの」を見つけ、同時に「変わるもの」の中から「変わらないもの」を見出して科学技術の原理や法則の確立とその実用化がなされてきた。今、改めて「量子」分野はその最前線の一つとなっている。若い人たちは、眼前の実生活を上手く生きるすべは身に付けながら、いわゆる「現状・現物・現場」から遊離はせずに、それだけではなく、ひたすら将来世界を洞察する力を養い、先々への果敢な挑戦を実践していってもらいたいと願っている」