荒井 慧悟(あらい・けいご)
東京工業大学工学院 助教
1986年福岡県生まれ。筑波大学附属高等学校卒。2008年東京大学理学部物理学科卒業。2016年マサチューセッツ工科大学物理学博士課程修了(Ph.D.)。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターでポストドクトラル・フェローとして量子センシング・コンピューティングの研究に従事した後、ボストン・コンサルティング・グループを経て、2020年2月から現職。

東京工業大学工学院 助教 荒井 慧悟
量子力学的効果を利用して、感度や空間分解能を物理法則の限界まで高められる次世代センサーとして注目されている量子センサー。温度や圧力、磁場、電場など外界のさまざまな環境から影響を受けやすい特性から、1つのセンサーで複数の物理量をマルチモーダルに測定できるとして、ITデバイスや自動車、医療機器などあらゆる産業界からの期待を集める。
東京工業大学の波多野・岩﨑研究室では、ダイヤモンドを用いた固体量子センサーを研究。これはダイヤモンドの炭素原子が置換した窒素原子(Nitrogen)と炭素の抜けた空孔(Vacancy)が非常に安定した構造「NVセンタ」を形成し、原子サイズの空間に閉じ込められた電子スピンに特異的な量子状態が出現することを利用したセンサーだ。
波多野・岩﨑研究室で、このNVセンタを研究する助教の荒井慧悟さんは、物理学者としては少々異色の経歴を持つ。前職は世界的ビジネスコンサルティング会社のボストン・コンサルティング・グループのコンサルタント。その前はMIT(マサチューセッツ工科大学)の大学院に在籍したまま、ハーバード大学の大学院で黎明期のNVセンタの研究に没頭。さらにその前はMITで世界のエネルギー問題を解決すべくプラズマ核融合に挑んでいた。
振り幅の大きい経歴だが、その中心には量子というなんとも奇妙で魅力的な世界があった。
(取材・文・撮影:佐藤さとる)
物心ついた頃には物理への興味を持っていたという荒井さん。量子という未知との遭遇は、中学時代ふらりと立ち寄った書店で手に取った本。そこには好奇心旺盛な中学生を魅了する、魔法のような世界が広がっていた――。
「中学生時代、たまたま立ち寄った本屋で相対性理論とか量子論の本を手に取ったんです。そこで物理の世界に興味を持ち始めました。
この世の中には、時間や空間が歪むとか粒子が壁を通り抜けるとか、奇妙なことがあるのだなと思ったのと、こんな奇妙なことを考える物理学者というのは、なんだか面白い人たちだな、と思った記憶があります。
明確な原体験は、高校時代に読んだブライアン・グリーンさんの「エレガントな宇宙」という本。難しかったのですがワクワクしながら読んで、大学で物理を学ぼうと決めました」
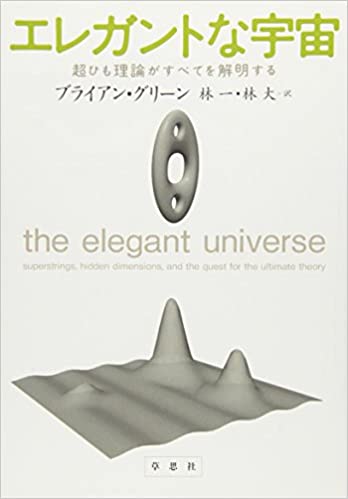
「その後、東京大学教養学部1年生のときに受けた清水明先生の授業でさらに量子論への興味が深まりました。
清水先生が執筆された『量子論の基礎』という本で授業が進むのですが、衝撃的な面白さでした。量子論の全体像をプロの視点から大学1年生にも分かりやすく解説した本で、いままで奇妙だと思ってたことがさらに奇妙になっている(笑)。いまでも量子論の本質は全く理解できていませんが、大学1年生なりに『すごい、理解できたぞっ』ていう感覚に陥ったんですね。それで本気で勉強しようと思うようになりました」
「衝撃的に面白かった」量子論。そのまま量子の世界に進むかと思ったが、荒井さんが3年時に志したのはプラズマ物理だった。量子論より実社会に貢献できそうというのが大きな理由だった。荒井さんは当時世界的プラズマ核融合研究の拠点でもあったアメリカMITの大学院に進む。
「量子論の奇妙な世界に興味がありましたが、大学の学部のときは社会の役に立つ物理学を勉強したいと思い、プラズマ物理を志したんですね。もともと自分にはどこか二面性があって、物理とは別に国際化とか、ボランティア活動とか、社会に役立つような活動にとても興味があったんです。かといって自分が何かできていたわけではないですが……。ただ若造なりに世界のエネルギー問題や人口問題などを、情熱を持って勉強していました。
そんな背景もあってプラズマ物理は、自分が世界のエネルギー問題をプラズマ核融合で解決するつもりで一生懸命勉強しました。そんな折、海外に留学する機会を得たんです。プラズマ物理学者の高瀬雄一先生を始め、世界的に有名な先生方に推薦状を書いていただき、それでMITの大学院に合格することができました。
MITに入学したものの、1年目の研究はあまり鳴かず飛ばすという感じで、同時期に受けていた量子論と相対論を融合する素粒子理論や量子論を応用した原子分子物理学など、学部までとは異なる毛色の物理学を勉強し始めたんです。その過程で、自分はやっぱり量子論に強い興味があると気づき、いったん社会への貢献は置いといて、量子論をしっかり研究してみたいと考えるようになり、大学院3年目にして、MITの学生でありながらハーバード大学の研究室に在籍することになりました」
「量子の研究に取り組みたいと思った中で、ちょうどハーバード大学・MIT界隈でいまの研究テーマに通じる、ダイヤモンド中の窒素-空孔というNVセンタの研究が盛り上がりつつあったんです。比較的実験が簡単にセットアップできて、結果もすぐ出そうな分野がいいなと思っていたので、そういう少し打算的な思惑で(笑) NVセンタを選びました。
量子を扱う原子分子物理学の分野ですと、例えば気体状態の原子や分子を何らかの形でトラップ(捕捉)して集め、それからようやくその特徴を探る実験に移れるのですが、まずトラップして集めるところで3〜4年かかったりすることもあるんですね。職人のような高度な実験技術が要求される世界ですので、大学院3年目から+3年でそれは危険だなと思いました。でもNVセンタだったら固体のダイヤモンドの中に自然にトラップされているような量子系ですので、最初の数年間を飛ばしてすぐに実験ができそうだということから、飛びつきました」
荒井さんはそのままMITに籍を置きながらハーバード大で研究を続け、ドクター修得(MIT)後もポスドク(博士研究員)としてハーバード大に残った。そのまま大学の物理学者の道を進むかと思いきや、そこから世界的経営コンサルティング会社、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)に入社する。思い切った転身だが、荒井さんには秘めた狙いがあった。
「ハーバード大学には5年間通い、プラス1年間ポスドクとして研究を続けまして、2017年から外資系コンサルティング企業、ボストン・コンサルティング・グループに入社しました。
ポスドクをしていた2016年当時は、NVセンタの応用研究がようやく始まったばかりで社会実装までの道筋が不透明だった頃。社会貢献の視点からすると、本当にこの技術を社会に送り出せるのかと疑っている自分もいました。このまま迷いながら自己満足で研究を続けるのも良くないと感じ、いったん何か新しい風を取り入れたくて、コンサルティング業界に入ったのです。
もともとコンサルティング業界には興味がありました。できれば量子センサ―のような新しい科学技術がどのように社会に広がっていくのか、そのために企業ではどのような意思決定が展開され、その実行にどのような組織力学が働いているのかを知りたいと思っていました。でもそんな都合よく学べるとは思えなかったので、とりあえずこれまでの研究は全て忘れてコンサルティングという大海原に出て、流されるままにいろいろなことに挑戦しました。
さまざまな業界のプロジェクトに従事するうちに、少しずつ新しいテクノロジーがどのように企業に浸透していくのか、ITやデジタル技術を今後どう活用していけばよいのかといった、時代の流れと企業の意思決定の力学が見えるようになりました」
3年後、荒井さんはBCGを退社。現在の東京工業大学工学院波多野・岩﨑研究室に転職する。再びアカデミアの最前線に戻り、ハーバード時代に取り組んだNVセンタの研究に打ち込みながら、学生の授業や指導、企業との連携などを模索している。
「3年で辞めたのは、さまざまな業界のプロジェクトを一通り経験できたと感じたので。まだまだやり残したことがいっぱいありますし、未熟でしたが、コンサルティングのお仕事を通して学んだことをアカデミアの世界で活かせないだろうかと思い、決断しました。
いま所属している研究室の波多野睦子先生と岩﨑孝之先生は、NVセンタの研究に長年取り組んでおられて、私自身がハーバード時代に行っていた研究に近い部分もありますし、また違う部分もある。当時からインパクトのある研究をたくさん発表されていて、面白そうだなと思っていました。お二人は私が留学していた頃にハーバード大学の研究室まで遊びに来てくださり、そこでいろいろなお話をさせていただきました。
NVセンタは、ダイヤモンドの結晶中にきれいな電子系が自然にトラップされている形になっており、普通の環境で単一のNVセンタを簡単に制御することができる特長があります。コンピューティングとかネットワークなど応用分野はいくつかありますが、センシングは最も社会実装に近い分野と考えています。
ダイヤモンドは極限環境でも比較的高い感度でセンシングができるのが強みで、NVセンタは既存の多くのセンサーよりも高温高圧の環境で機能するセンサーになります。
もう1つの強みはセンサーのマルチモーダル化です。例えばスマートフォンの中にはセンサーが十数個も入っています。数が多いのはそれだけ多様な機能が求められるからですが、古典的センサーには磁場しか測れないとか、温度しか測れないという限界があることも原因です。量子センサーになれば、基本的に量子という非常に外界から影響を受けやすい系で、電場や磁場をかけても、温度を変えても変化するので、そこをうまく独立させて情報を取り出せれば、いろいろな物理量が測れるマルチモーダルなセンサーとして使えるようになります。もしこれが実現すると、1つの製品のセンサーの数が減るのでスペースが有効活用できたり、システムをシンプルにすることが可能になります。実現するのはなかなか難しいと思いますけども、世の中に多々あるセンサーを一部リプレイス(置き換え)できる可能性もあります」
中学時代、ふらりと寄った書店で出会った1冊の本で量子の世界に魅せられた荒井少年。プラズマ物理学やボランティア活動、コンサルティングなど社会に貢献したいという思いを実現するために、アカデミアと実業を行き来してきたが、現在は気鋭の若手物理学者として国家プロジェクトの「Qリープ(Q-LEAP)=光・量子飛躍フラッグシッププログラム」のメンバーなど、まさに“一周回って”量子ICTのフロンティアをリードする役に。
振り幅の大きい経歴で得た濃密な知的生産の知見を武器に、荒井さんはワーク・ライフ・バランスの範を示しながら、世界の量子ICTシーンのフロンティア開拓と次世代量子ネイティブの育成を図っている。
「量子の科学技術応用はいくつかありますが、センシングはその1つで、NVセンタの場合、固体であるダイヤモンドの中にきれいな電子系がトラップされているようなものなので、私たちが生活しているような常温常圧環境で単一のNVセンタを精密に制御することができるのです。
そこに情報を蓄えて読み出すと量子コンピューティングに応用できたり、情報を光などの媒体に載せて飛ばすと量子ネットワークに応用できたりする可能性があります。センシングは、その系に磁場をかけたり電場をかけたりするとNVセンタの性質が変わるので、その変わった性質を読み出して、逆にかかった磁場などを定量的に評価することになります。その研究をしています。
量子センシングは、常温で多少ノイズが入ったとしても比較的高い感度が出て、なおかつ量子の強みである1個ずつの制御や、非常に小さい領域での磁場や電場をセンシングできる。なので基礎科学にも応用ができますし、さまざまな研究テーマが広がる、魅力的な分野です」

「可能性は大いにあると思います。いま使われているセンサーの多くが従来型の古典的センサーですが、古典的センサーの欠点の1つは、電気回路で構成されていたり、磁気回路での構成のために、高熱や高圧をかけるとその特性が壊れてしまうこと。
一方で量子センシングの中でもNVセンタのセンサーの場合は、ダイヤモンドを使っているため高温高圧でも比較的高い感度でセンシングができる。
いままで常温域でしか使えなかったセンサーが極限環境にも進出できるので、取れるデータの対象がどんどん拡大していく。IoT化の世界を大きく変えると考えられています。
もう1つの強みは、センサーのマルチモーダル化です。基本的に量子は非常に外界から影響を受けやすいので、電場をかけても磁場をかけても変わるし、温度を変えても変わる。量子センサーはその性質をうまく利用するのです。それぞれの影響を独立させて情報として取り出せれば、いろんなものが測れるマルチモーダルなセンサーになります。
例えば工場のモニタリングで温度と圧力を測ろうと思えば、2つの計器を違う場所に付ける必要があるために完全に同じ地点でこれらを測ることはできませんが、量子センサーならそれができる。
今日の世界はデジタルツインやサイバーフィジカル空間といった技術が進んでいます。今後バーチャル空間上の情報量が一気に増えていく中で、1個で複数のデータが取れるマルチモーダルな量子センサーに期待が高まっています」

「まず全体クールは1日7時間で週5日。割合としては、そのクールの約6割が研究活動で2割が教育活動、1割が大学の事務ですね。残りの1割が企業や大学外部の方とのやり取りみたいな感じになっています。1日のスケジュールとしては朝7時から大学で仕事をしています。
最初の1時間は、その日にやるべきことになるべく取り組むようにしています。1番のコアタイムです。7時から8時半までは内容はまちまちで、企業の方と会うときのアイディアを練ったり、学生さんの指導をする上での準備とか、論文の重要な要旨を書いたりとか。バラバラですけれどその時々で優先度の高い、集中力が必要なことに取り組んでいます。
8時半から9時半は子どもの保育園の送迎があって、9時半から12時まではミーティングが入ることが多いです。研究室内の学生さんのチームミーティングが毎日1、2回あります。その合間にいろいろ研究を進めたり事務作業もこなしています。
午後は1時頃までに昼食を取り、3時半までは実験をしたり、授業や実験の準備、雑用に回したりなどさまざまに時間を使っています。論文の執筆で忙しいときは午後を丸々充てることもあります。ミーティングはなるべく入れないようにしていますが、Q-LEAPのミーティングが入ることもあります。
そして3時半に子どもを迎えに行って1日が終わり、という感じです」
「休日も研究しようと思えば可能ですが、自分の働き方改革もあって休むようにしています。
もともとすごく働くタイプなんです。大学院の頃は朝8時に来て翌日の明け方まで研究していることもよくありました。それこそマイナス20度にもなる真冬のボストンで、誰もいない雪道を自転車を走らせて帰ることも多かったです。土日もほとんど働いて、年明けやクリスマスをクリーンルームですごしたりとかずっと研究一筋でして。
また、ボストン・コンサルティング時代も自らの意思で長時間働いていました。
意識が変わったのは子どもができてから。いま1歳と0歳なんです。いままでと同じように研究に長時間費やせば、相応の業績も出るかもしれませんし、そういった働き方に慣れていたので、自分自身も楽でストレスも逆にたまらないです。が、ただ、そういう働き方だと学生さんにも無言のプレッシャーを与えかねないですし。あと、人生の先輩方から、子どもはあっという間に成長するから、子どもとの時間を取らないと後悔するよと伺って、意識的に時間を取るように変えました。
それで限られた1日の時間の中で、研究や教育効果を最大化するためにはどうすべきかを一生懸命考えるようになりました」
「役立っていると日々実感しています。研究もコンサルティングも知的生産という点では共通してるんです。研究の場合は、自然科学に対して誰も解いたことがない問題設定をして解いていく世界。一方、コンサルティングは一流企業でも難しい課題について外部から入って短期間で解かなければならないという厳しい世界。
コンサルティング会社の場合は知的生産の方法が体系化されていて、しかもそのトレーニング方法も確立されていました。そこで学んだことを自分なりに咀嚼して、研究や教育にも活かせないかと、この2年ぐらいずっと試行錯誤しています。いまの学生さんには実験台になってもらってます。申し訳ないんですけども(笑)」
「非常に重要な組織だと思います。やや抽象的な話ですが、僕自身は世界の中で日本のあらゆる競争力が落ちてきているのを非常に危惧していて、そういった中で実際に日本が競争力を回復するための打ち手の1つとして量子があると考えています。ですから量子をしっかり推進していく上で、ある程度のモメンタムを持ったICTフォーラムは非常に重要な役割を担っていると思っています。
逆に言うと、量子ICTフォーラムの動きが、今後日本が競争力を回復できるかどうかについて1つのカギを握っていると考えています。
日本の競争力が落ちている中では、海外に対して付加価値を持った概念なり製品なりを生み出していかないと、今後は海外からどんどん搾取をされかねない。そこで何かしら付加価値のあるものを作っていくとなると、現実的にはデジタルでも人工知能でも追いつくのが困難な状況になっている。しかし量子に関してはまだ世界をリードできる可能性が大いに残されています」

「もちろん量子コンピュータはカナダ・アメリカがすでにビジネス化していますが、基礎技術は日本が非常に進んでいるし、戦略的に取り組めばいまからでも遅くない分野だと認識しています。
あと10年20年は競争が続くので、いままでのように産官学で連携するに留まらず、3者が1体となって推進していく方向を探らないといけないのかなと思います。
量子にはすごく期待をしていますし、自分自身も何かしらの貢献ができるよう、研究に取り組んでいきたいです」
「そうです。日本はここ20年くらいあまり変化がなく、安定して穏やかで、とても住みやすい。一方でアメリカの変化の速さには圧倒されました。
例えばボストンは僕が留学してる間にも治安が目に見えて改善したり、バイオテックのシリコンバレーとして急成長しました。劇的にどんどん変わっていったんです。
普通に大学の街だったのが、どんどん製薬企業が移転して来てアクセラレータやインキュベーターが入って、スタートアップも雨後の筍のように立ち上がっていった。中国人の友人の話を聞くと中国の深センはさらに目まぐるしく発展しているといいます。東南アジアもインドも中東もどんどんそういった変化が起こっている。それを知り、日本も成長させたいと思ったんです」
「やはり大学院の指導教官から大きな影響を受けています。ハーバード時代の先生で、いまメリーランド大学におられるロナルド・ウォルズワース(Ronald Walsworth)教授です。
自分がこういう研究者・指導者になりたいっていう理想像に近い方で、研究の楽しさや考え方、世界のものの見方を学びました。
1つ印象に残っているのは、ある日の夜中にひとりで実験をしていたときに、2時を回った頃に珍しく彼が実験室に入って来ました。僕を見つけると嬉しそうに近寄ってきてニコニコしながらこんな話をしてくれたんです。
『君もあと10年もしないうちに結婚して子どもも生まれて、学生ができて、お金のことや保険のこととか、さまざまな悩みがどんどん増えるだろう。そんなことを一切気にせず研究に脳みそを100%使えるのはいまだけだよ』と言ってくれて。もちろん長時間労働を勧めているわけじゃないんですけども、『いまが1番楽しいし将来的に思い出にも残るから、満足するまで好きなだけ研究に没頭しなさい』と。
そのときはもう2時だから早く帰りたいし、すでに博士課程の悩みで頭がいっぱいだと思ったんですけども、結婚して子どもができたいま、少しずつ分かってきたかなと思います」
「アメリカの研究者の考え方として、ワーク・ライフ・バランスを取るのは当たり前として刷り込まれています。ただ日本のように画一的に何時までに帰りなさい、年間何日は休みを取りなさいということではなく、自分なりの基準をしっかり持ってワークとライフをバランスしなさいということなんです。だから人によっては、本当にいまはワーク100%だという人もいます。個々の理想の働き方を尊重して多様な働き方を認めているという感じです。
個人的な意見ですが、研究者の働き方はアーティストとかプロスポーツ選手、お医者さんの働き方に近いと思うんです。どの職業もある時間働けば一定の収入が安定して得られるというものではないので、ワーク・ライフ・バランスは自分で定義して、たとえ世間が休みであっても鍛錬を欠かさない働き方をしていると思います。
研究者もそれに近い部分があって、完全に休むとどうしてもそこで思考が途切れてしまう。毎日少しずつでも考えていけば思考が累積されて、いつかブレイクスルーに到達します。仕事がある程度まとまるまでは、なるべく休まず没頭し続けるというのが、個人的には生産性の高い働き方のスタイルです」

「次世代の人材育成という観点では、新しい世代の方に望むことが3つほどあります。
1つは、量子で世界に付加価値をもたらせる人材になってほしい。僕自身もそういう人材を育てていきたいという希望があります。
そのためには知的生産の考え方をしっかり身に付けて、世界の研究者たちと互角に渡り合える生産性で、どんどんアウトプットを出すことが避けられません。
2つ目も個人的な願望ですが、プロフェッショナリズムの意識を持ってほしい。
顧客や社会に付加価値を提供した対価としてお金を稼ぐという意識がプロフェッショナルな量子人材だと考えています。
そのために必要であれば効率的に勉強をする。自己成長やスキル習得は目標や目的ではなくて、社会に付加価値を提供するための手段であるという考え方です。すると長時間働かなくとも負い目を感じることがないので、結果として健康に働けると思うんです。
3つ目は量子とは一見関係ないかもしれませんが、物事を言語化する力を養ってほしい。
理系の学生さんは、数学をフィーリングで解いて勝ち残ってこられたような優秀な方も多いです。文系の学生さんだったら入社後に受けるような、分かりやすい報告書を書くトレーニングを受ける機会が少ないと思うんです。
でも量子の発展を考えると、研究者や専門家は量子の大切さを研究業界だけではなく、産業や官を含む社会に広く届ける必要がある。それには人類がこれまで培ってきた言語という最も優れた情報伝達ツールを通じて論理的に分かりやすく説明しないといけない。そういった能力を理系の人ほど身に付けてほしいと思います」
「まさにその辺のことを自分なりに分析してみたんです。専門的な内容を一般の方に伝えるのが難しいのは、専門的な概念が難しいからでなく、コミュニケーションの目的に応じて適切な粒度の情報を適切な論理展開で言語化するのが難しいからなのではないかと思います。最も単純な例でいうと、文章のトップダウン化が挙げられます。英語圏の方々はトップダウン式に文章を組むんです。例えば『AはBとCから算出される。BはDで定義され、CはEで計測される』というように、文がピラミッド構造になっているのが基本系で、文を集めたパラグラフもピラミッドになるし、パラグラフを集めた章も、章を集めた本もピラミッド構造になる。それがいまの急速に発展する社会においては最も効率良く情報を人に伝える構造になっている。
だから欧米の人はコミュニケーションにおいては強い。一方で日本語の場合はボトムアップ式にも表現できて、それが許される曖昧さがあります。
『BとCから算出されるのはAである。ここでDを用いてBを定義し、EでCを計測する』というボトムアップ的な表現も十分に通じる。だから論理構造を意識せずにボトムアップで書いてしまう学生さんは結構多いんです。
日々の研究報告でも、自分の身の回りに起きたことから話をしたいので、詳細から述べてその結果こうなりましたっていう説明をする学生さんが多いんです。しばらく話を聞いて、あの計測のことを話題にしているのか、とようやく判明する。僕もそうなんですけども……。
ボトムアップ型の文章だと、話のトピックや要点がわかりにくくなって多くの人に読んでもらえず、自分の書いた文章の影響力が限定的になってしまう。
僕は文章の影響力は研究者が提供できる付加価値の一部だと思うので、同じ時間をかけてやっているのに欧米人より付加価値が小さくなってしまう。そこが日本人の労働生産性が低いといったことにも繋がってくる。
今後特に理系の方には、論理的文章構成力を欧米人と同じようなトップダウンにしていくことが求められるのかなと思います」

「英語が喋れるかどうかという問題は、自動翻訳技術の発展に伴って、別に苦ではなくなる時代がすぐ来ると思うんです。ただ欧米式の論理構造で物事をアウトプットするという点においては、まだまだ機械では難しいと思いますので、そこを理解して身に付けるようにすることが大切になってくると思います」
「また抽象的な話題ですが、メタ的な問いを投げかけることだと思っています。例えばどうすれば研究者として上の人や業界から評価してもらえるかとか、どうやったら効率的に働けるかみたいに、自分自身の思考や振る舞いを一歩引いて客観的に考えるのがメタ的思考です。そこを意識して研究に取り組む学生さんはあまり多くないと感じています。
例えばいまの時代はインターネットに情報がいくらでも落ちているのに、自分が必要としている情報にたどり着けないんです。自分が知っている単語で検索をかけても整理された使いやすい情報が出てこない。そこで思考を止めないで、自分が知らない領域に重要な情報があることを想像して、それにたどり着くためにはどんな問いを立てればよいだろうか、と思考を続けることが自分の世界を広げることに繋がると思います。
この装置はどうやって使うんですか、という1次元的な問いは誰でも思いつくと思いますが、それだけでなく、「論文を書くためにどういう視点で事前準備をしておいたらいいですか」といった、一段上の視点での質問ができるようになると、だいぶ成長が速くなると思います」

荒井 慧悟(あらい・けいご)
東京工業大学工学院 助教
1986年福岡県生まれ。筑波大学附属高等学校卒。2008年東京大学理学部物理学科卒業。2016年マサチューセッツ工科大学物理学博士課程修了(Ph.D.)。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターでポストドクトラル・フェローとして量子センシング・コンピューティングの研究に従事した後、ボストン・コンサルティング・グループを経て、2020年2月から現職。