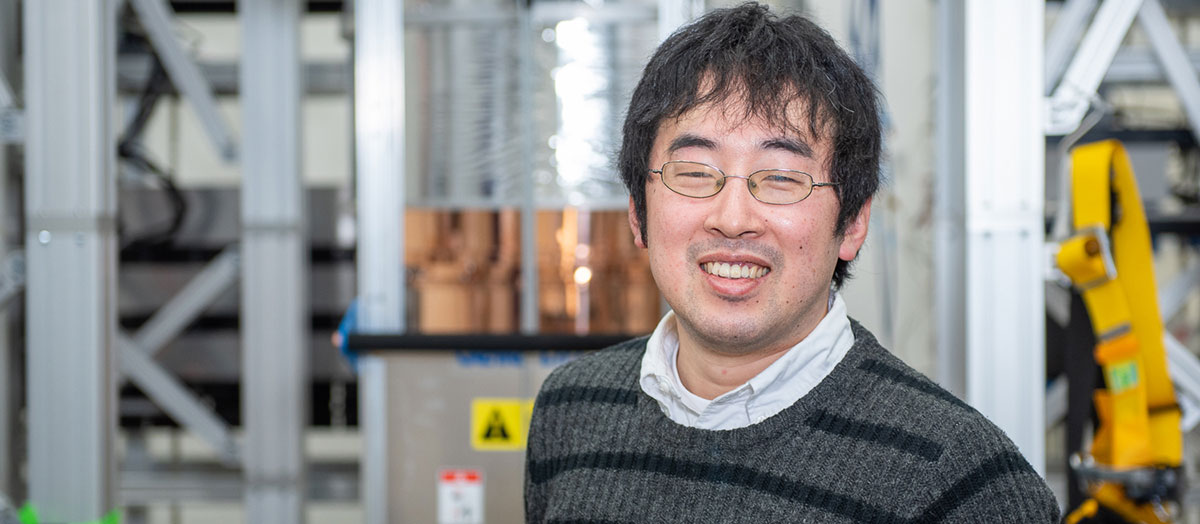
量子コンピュータ技術推進委員会若手インタビュー システム全体の性能と拡張性向上で挑むデジタル量子コンピューティングの実現
理化学研究所量子コンピュータ研究センター
超伝導量子計算システム研究ユニット ユニットリーダー 田渕 豊
―近年、量子コンピュータを取り巻く環境は大きく変化している。
最前線で研究を進める研究者は、今の世界をどう見て、未来をどう作り上げていくのか。本連載では、日本で量子コンピュータ技術の研究開発において活躍する若手研究者の声から、量子コンピュータにまつわる様々な視点を届けていく。
量子コンピュータの実用化には、まだ多くの解決すべき課題がある。量子コンピューティングの未来を切り開くためには、単に物理量子ビットの数を増やすだけでは不十分であり、それらを統合し、高い計算能力を実現するための緻密な設計と誤り訂正技術の確立が必要不可欠とされる。
こうした課題に超伝導量子ビットの集積化の研究を通じて挑んでいるのが、理化学研究所量子コンピュータ研究センターの田渕豊さんだ。田渕さんが率いる研究チームは、超伝導量子回路の設計をシステムレベルで統合し、素子全体の性能と拡張性の向上を目指す。今回、田渕さんが見据える量子コンピューティングの進化の軌跡や、その実現に向けた研究の挑戦についてお話を伺った。
(聞き手・構成・撮影:小泉真治)
量子世界の魅力に引き込まれた“ある一言”

――量子の分野に興味を持たれたきっかけを教えてください。
きっかけは、高専時代に遡ります。私は情報工学を専攻して、コンピュータの実装や暗号について学んでいました。そのとき、数学の先生が素因数分解の問題を扱い「量子コンピュータであればこれが一瞬で解ける」と説明されたんです。当時、自主ゼミでRSA暗号を実装した際に「この複雑な暗号を解くのは相当大変だろうな」と実感があったため、量子コンピュータなら簡単に解けるという先生の言葉は、非常に印象的でした。そこで量子コンピュータに関するリサーチを始めたのが興味の始まりです。
その後、大学への編入を検討する過程で、量子情報について研究ができる場所を調べるうちに、大阪大学の北川勝浩先生のことを知り、その取り組みに惹かれるようになりました。そこで編入先を大阪大学に決め、北川研究室で核スピンを使った量子コンピュータの研究を始めました。
最初に取り組んだのは、核スピンについての研究でした。基本的には、電波を核スピンに当てて信号を読み取るという方法です。ただ、信号の波形がひずんでいると、スピンを正確に制御することができません。そこで、このひずみをどう除去するかが私の研究の一つの焦点でした。
並行して、電子スピンの研究も行いました。電子スピンは核スピンよりも高い周波数を使用します。この違いを活用し、どのように装置を構築し、電子スピンを制御できるかを探求しました。修士課程と博士過程を通じて、装置の設計から冷凍機の準備まで多岐にわたる作業を行いながら、自由な環境で研究を進めることができました。
――それから現在の研究に至るまでにどういう経緯があったのですか?
2011年、NECの基礎研究所にいらした中村泰信先生の下でインターンシップを行う機会があり、超電導回路の研究に携わりました。超電導回路は、低温環境やマイクロ波など、電子スピンと非常に似た技術を使います。ただ量子ビットが変わっただけで、技術的な類似点が多く、非常に魅力を感じました。その後、中村先生が東京大学に移られる際、私も博士課程修了のタイミングだったため、一緒に参加させていただきました。
そして2016年には、ERATOの中村巨視的量子機械プロジェクトに参加しました。このプロジェクトは、量子コンピュータの集積化に向けた本格的な取り組みとしては、日本で初めてのものです。それ以前から世界的に量子コンピュータ研究の熱が高まっているのを見て、自分も集積化の研究をしてみたいと思っていたため、プロジェクトがスタートしたときは感慨深かったですね。それから現在に至るまで、量子コンピュータの集積化に関する研究を続けています。
スケーラビリティの革新に向けた後発組からの挑戦

――現在取り組まれている研究の概要を教えてください。
私の主な研究テーマは、簡単に言うと「量子ビットの数を増やす」ことです。量子ビットを効率的に、かつ正確に増やすにはどうすれば良いかを研究しています。具体的には、拡張性に優れた素子を使って、システムの拡大が容易にできる技術を開発しました。
拡張性を高めるには、量子ビットのデザインの段階で、チップをスマートに設計することが大切です。そうしなければ、配線が複雑に絡まってしまい、システムのスケールは困難です。そこで私たちは「タイラブルデザイン」を開発しました。これは、基礎設計をタイル状に並べて拡張するもので、チップやゲート、配線を含めてシステム全体が容易に拡張できます。また、拡張の際に再度配線層を設計する必要がなく、作業工程を削減できるのもメリットの一つですね。この設計により、2018年の1ビットから始まり、2022年には64ビットまで拡張することができました。
こうしたシステムの拡張性についての技術が、最近になって外部からも評価され始めています。また、私たちの設計方法が企業に共有されることで、さらに大規模なシステムの開発が進められる方針です。
――タイラブルデザインの開発に成功した要因は何だと思われますか?
それは、後発組であることの利点を生かせたからだと思います。中国のスーパーコンピューター開発の成功例が示すように、古いレガシーがない状態では、新しい技術やアプローチを素早く取り入れ、開発を進めることができます。
私たちも同様に、後発組としての立場を活かし、古い資産に縛られることなく、配線の問題を独自の方法で解決するといった新しい設計哲学を採用できたのは、大きな利点だったと感じています。さらに、適切なタイミングで必要な予算と人材が揃ったのも追い風となったのではないでしょうか。
――この技術の応用が広がれば、スケーラブルな量子コンピュータの実現に大きく貢献しそうですね。
そうですね。この技術がなかった場合のデメリットを考えると、わかりやすいかもしれません。大規模化に伴う配線間での混信は、システムが大きくなるほど顕著な問題となります。この問題を解決することなく、量子コンピュータを大規模化しようとすると、計算の正確性が著しく低下することが予想されます。そこで私たちの技術によって、これらの配線問題を効果的に解決し、信号の混信を最小限に抑えられるというわけです。
量子コンピュータの研究と言うと、多くの人は量子コンピュータそのものの製作に注目しがちですが、その背後にある設計方法論やプロセスの革新にこそ、真の価値があると私は考えています。つまり、大切なのは量子コンピュータをつくること自体ではなく、その「つくり方」を研究して開発することです。確かに量子コンピュータをつくることは技術的な挑戦ではあるものの、実現手法をゼロから構築し、そのプロセス自体に革新をもたらすことは、遥かに困難な課題です。そこが研究の面白さでもあると思っています。
量子コンピュータのデジタル化がもたらすシンギュラリティ

――今後取り組みたい研究やプロジェクトについて、具体的な計画や目標をお聞かせいただけますか?
量子コンピュータの性能向上に向けては、タイラブルデザインの枠組みを超える、次世代の手法の開発が必要だと考えています。そこで現在は、タイラブルデザインの研究に並行しながら、100万量子ビットを実現するための新たな手法の探求を、JSTの推進するムーンショット型研究開発事業のプロジェクトとして進めています。
既存の手法でも1000ビット程度までなら比較的容易に実現できるはずですが、100万量子ビットとなると、やはり難しい。100万量子ビットに向けて必要なコンポーネントを洗い出してみると、低温で動作するエレクトロニクスや新しいコンピュータアーキテクチャ、そして配線の省線化など、多岐にわたる分野の技術革新が必要なんですね。現在、こうした幅広い分野の研究者たちとの共同作業を通じて、100万量子ビットを目指す量子コンピュータの設計について議論を進めています。
また、量子コンピュータを実用化する上では、誤り訂正の取り組みは避けて通れない道だと考えています。実は、現在実現している量子コンピュータは、アナログコンピュータです。過去の歴史を見ても、アナログコンピュータはノイズに弱く、結果的にデジタルコンピュータに取って代わられました。量子コンピュータも同様に、スケールを考えるとデジタルの持つノイズに強いという性質が不可欠です。
デジタルではノイズがあっても、一定の閾値を超えれば正確な計算が可能です。この閾値を設けることができるのが、誤り訂正技術の役割です。誤り訂正技術によって、量子コンピュータはデジタルの特性を獲得し、より大規模で、より信頼性の高い計算が可能になるというわけです。量子コンピュータのデジタル化が、いわば一つの技術的特異点(シンギュラリティ)になるのではないかと思っています。
――デジタル量子コンピューティングの進展によって、どのような未来が開かれるのでしょうか?
実際のところ「わからない」というのが私の正直な考えです。そもそも、コンピュータの計算原理やパワーをまったく違うレベルに持っていくわけなので、何が起きるかわからない、何が起きてもおかしくないと思うんですね。
ちなみに、1950年代に開発された日本における古典コンピュータの初めてのソフトウェアは素因数分解ができるもので、次がフーリエ変換だったそうです。それから現在まで70年以上をかけて、今のようなソフトウェアの使い方へと成熟してきたわけです。量子コンピュータも同じような道をたどると思われ、人々が使いこなせるようになるまでには、相応の時間がかかると見込んでいます。
これまでも技術の想定外の使い方は数多くありましたし、量子インターネットが誕生したとして、その後の世界がどうなるかも読めません。量子コンピューティングの全容が明らかになるのは、まだ先のことだと思っています。
探求心でつなぐ次世代へのバトン

――研究の先にシンギュラリティが待っていると考えると、非常に魅力的ですね。そうした研究の醍醐味や、やりがいについてお聞かせください。
デジタル量子コンピューティングへの道は、確かに長くて険しいものですが、そのプロセス自体が非常に魅力的です。私たちが目指しているのは、計算の原理を根本から変えることであり、「これが実現すれば、何かすごいことが起きる」と想像するだけでワクワクしますね。
また、これまでの量子コンピュータは物理が主な研究分野でしたが、現在は電気系、回路系、システム設計やマイクロアーキテクチャなど、他の技術領域へとシフトしてきています。この変化を楽しむことも、研究を進める上での大きな魅力の一つです。
――研究を通じて目指す未来像や到達したいゴールについて、詳しく教えていただけますか?
量子コンピューティングにおいて、ゴールと言える終点は存在しないと考えています。この分野は、私一人や私たちの世代だけで完遂できるものではなく、多くの世代にわたる長期の研究が必要です。
その中で私の役目は、今手がけている研究の成果を次の世代に継承し、彼らがさらにその先を追求できるようにすることです。よく「Life is too short for quantum computing」と表現しているのですが、私に残された研究期間は、リタイアまでの時間を逆算すると、あと25年ほど。その間に可能な限り大きく前進させて、次の世代に知見を伝えることが、私にとってのゴールと言えますね。
ですので、今の20歳前後の若い世代は、量子コンピューティングの分野において、非常に面白い時期にいると思います。これからの10年で、量子コンピューティングの基礎がさらに固まり、その後の20年、30年と長期にわたり、この分野の発展を支えて主導していくことが可能になります。実用的な量子コンピュータの完成を目の当たりにして、さらなる応用の開発に貢献できるかもしれません。とても羨ましく思います。
――研究者としてお忙しい日々をお過ごしの中で、休日はどのようにリフレッシュされていますか?
休日は、家族と過ごすことが多いですね。平日はなかなか時間が取れないので、休日くらいはできる限り育児に参加して、少しでも妻をサポートできればと思っています。子どもたちとは、一緒に公園へ行ったり、小型コンピュータでプログラミングやゲームをしたり。雑談の中で、勉強する意味について一緒に考えたりもします。工作も好きで、よく弓矢や手裏剣といった武器をつくって遊んでいますよ(笑)。
「フリースケート」というローラースポーツを子どもと一緒に楽しむことも多いです。私はもともと、エクストリームスポーツと呼ばれるジャンルが好きで、これまでもスノーボードやBMXなどを趣味としてきました。それは「エクストリーム」とあるように、たまには羽目を外すようなことをしていないと、自分が“普通”になってしまう気がするからです。私は、遊び心を失ったら研究者として終わりだと思っているので、プライベートにおいても非日常的な刺激を探求し続けていきたいですね。